相川浩之
4月6日付で「書籍JANコード登録通知書」をいただき、出版社(会社組織にしていないので、正確には出版者)としてスタートすることになった。名前は「ジャーナリストの魂出版」。
出版を始めようなどとは41年間勤めた日本経済新聞社を2022年11月末に退職する時点では思ってもみなかった。新聞に書けなくなって、自分のメディアが欲しいと感じていた。そして、本というメディアを出す準備が整った。
新聞社は自分で新聞を印刷する。誰にも介入されずに、情報やオピニオンを発することができるのは、自分で新聞を発行するからだ。それと同じ。これからは「ジャーナリスト魂」を発揮しながら、取材し、自由に書いて発信していく。取材が困難でなかなか文章にできなくても、真実を追い求め、取材することには大きな意義があるはずだ。
出版社を始めることを決意するまでには、さまざまな人たちからの後押しがあった。退職後、やることなすことうまくいかず、ふらふらしていたのだが、こうした後押しのおかげで一歩が踏み出せた。
まず、刺激を受けたのは、大学病院の教授だったY君だ。地方都市の病院の院長となると手始めに、資料を集め、その病院を立ち上げた恩師の思いを体現する記念館を作った。そして、今後10年で病院を改革しようとしている。
外科医のなかでも他の医師を指導するほどの卓越した技術を持っていた彼は、その経験を地方都市の病院のレベルアップに生かそうとしている。
今年、通信社に記者として採用された高校の後輩に「ジャーナリストの勉強ができ、お金までもらえるなんてありがたいと思わなきゃ」とアドバイスした。今は本当にそんな気持ちだ。41年務めた新聞社は収入以上のものを私に与えてくれた。取材の仕方、原稿の書き方、そして、問題を見つけ、解決策をなんとか見出す方法を教えてくれた。世の中におかしなことがあれば、黙ってみていられない、そんなジャーナリスト魂はいまだ健在だ。
せっかく培ったジャーナリストとしての魂や技術を生かして、Y君のように新しいミッションに踏み出したい。
新聞記者の名刺がなくなると、取材が難しくなるのは事実だが、それでも取材の狙いと思いを告げれば、取材に応じてくれる人は必ずいる。困難な取材もたくさんしようと思っている。その困難さを伝えることも大切と考える。取材して、分かったことがわずかだったとしても、「分からないこと」の多さを書くこともできるだろう。新聞とは違う、表現のスタイルが書籍にはある。いろいろな表現を駆使して、伝える努力をしたい。
Y君が、新たなミッションに挑戦する姿を見せてくれたとすれば、ジャーナリストの心意気を改めて示してくれたのがジャーナリストの立石泰則さんだ。
『覇者の誤算 日米コンピュータ戦争の40年』(日本経済新聞社、講談社文庫)で第15回講談社ノンフィクション賞を受賞、その後もコンスタントに経済分野のノンフィクションを書き続けている。
池袋の梟書房で、開店の10時半から4時間も話し込んだ。楽しかった。 立石さんとは、彼がまだ週刊文春の記者だった時に一度お目にかかった。その後、私が編集長を務めていた月刊誌「日経ゼロワン」の1998年2月号で富田倫生さんと対談をしてもらった。お目にかかるのはそれ以来、もう25年も前だ!


立石さんは、1950年5月生まれ。週刊文春の記者を経て、1988年に独立。『復讐する神話〜松下幸之助の昭和史』(文藝春秋)でデビューした。その後も、『漂流する経営〜堤清二とセゾングループ』(同)など著名な経済人を取り上げた著書が多い。でも、「君は無名だから、著名な人を取りあげなさい」と出版社に言われただけで、特に経済界のノンフィクションを書いていこうと思っていたわけではなかったらしい。しかし、このジャンルのものを書いてほしいという要望が多く、結果的に経済物が多くなったという。
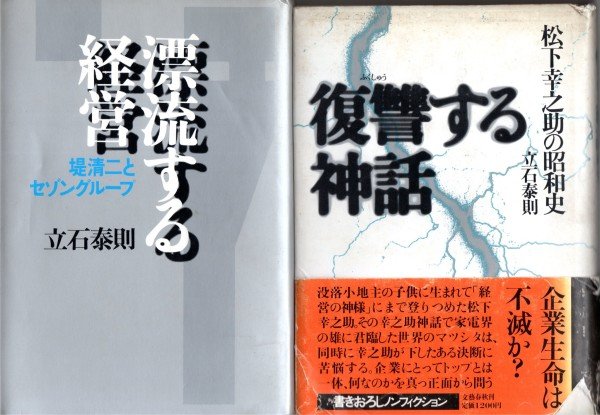
私は「生活ジャーナリスト」と名乗っていた。日経の生活情報部(退職する時は生活情報グループ)で暮らし関係の記事を書いていたし、日経トレンディ、日経ゼロワンなど手がけていた雑誌も生活周りのテーマが中心だった。それで、そう名乗ったのだが、「肩書きで仕事を制約しない方がいい。『ジャーナリスト』とだけ名乗り、好きなことを書けばいい」と彼にアドバイスされた。
目から鱗が落ちた。フリーなのだから何を取材してもいい。
彼はノンフィクションを書く時には、徹底的に資料にあたる。例えば堤清二の書いたものは小説や詩、同人誌への寄稿まで全て読んだという。関係者には徹底的にインタビューする。「日本人は印刷されているものをすぐに信じる傾向があるが、複数の資料をあたって、本当に正しいか吟味しなければいけない」「特に公文書は間違いだらけ。◯月◯日に就任と言った記録でさえ間違っていることが多い。別の資料や本人に聞くなどして、補完しなければいけない」。権威を疑うというのは彼のおじいさんの影響も大きいという。おじいさんは「政府の言ったことの真逆が真実と思えば、だいたい正しい」「『先生』とよばれる人は信じないほうがいい」と教えてくれたという。彼はパナソニックやソニーなど家電業界の経営者を取り上げているが、経営者たちの一挙手一投足ばかりを細かく描いているわけではない。彼らが生きる産業界や時代の変化についても詳しくならなければ、ノンフィクションは書けない。だから、彼は、大きな時代の流れについて、いつも考えている。なぜ家電メーカーがかつてのような力を失ってしまったのか。その一つの原因が国際的な水平分業。日本の産業構造にとってはマイナス面もあった。ものづくりをするところに、技術(力)が蓄積するからだ。
AIで日本は成長できる?「SNSに書かれたことなどをAIが学んでいく。だから、SNSをアメリカ企業に牛耳られている以上、日本はアメリカにはAIでは太刀打ちできない。対抗できるのは独自のSNSを育てている中国くらい」「日本はAIではできない分野で、独自の新事業を起こすしかない」。
立石さんは「事実をきちんと調べて書いておけば、次の世代の若者がさらに事実を深めてくれる」と期待する。「努力して取材しても、わからないことは必ず残る。それは次の世代に深めてもらえばいい」。次代の人に残す。ジャーナリストは歴史を書いているのだなあと思った。いま、我々、ジャーナリストがやらなければならないのは、「事実をきちんと明らかにして書き残すこと」なのだ。
本を書いたら数人しか読んでくれなかったらどうしようと思う」と弱気なことを言ったら、「相川さんは本を売りたいの?事実を残すことを目的にすべき。いきなり多くの人に読んでもらいたいなどとあまり考えない方がいい。まず一人の人に読んでもらえるものを書くことが大事」と言われた。「ジャーナリストは後世まで残せることを書くことに価値がある」(立石さん)。そうか。そうだよな。気が楽になった。どれだけ読まれるかなどと考えても、いいことはない。受けなどは狙わず、自分が書きたいことを誠実に書いてみよう。
立石さん、SNSについて聞くと、否定的なコメント。「議論には向かない。告知のメディアではないか」。「SNSの普及で日本語も乱れてきた。刺々しい言葉ではなく、優雅な言葉を読みたい」。「優雅な文章を書くには、志賀直哉や夏目漱石、芥川龍之介と言った古典の文章をを読んで、気に入ったフレーズを書き残しておくと良い」という。
事実の掘り起こしはキリがないと思うがどうすればいい?「関心のあることを納得するまで調べるしかないのでは。そのためには、好奇心は不可欠」(立石さん)。そして、「本質は何か」と考える癖をつける必要がある。これが非常に難しい。仕事柄もあって、新しさ(新しそうなこと)にばかり目を奪われがちだったが、本質をつかめないとジャーナリストとして生きていけない。近道はなく、「例えば古典の名著を読みながら考える」訓練が必要だという。
「繰り返し読みたくなるような本もある」という。例えば、マルク・ブロックの『奇妙な敗北』。読書は平日は仕事に関係のある本を読むが、土日には、古典の名著などを読むという。立石さんは72歳になった今でも「毎年一冊本を書く」ことを目標にしている」という。でも、生に執着はないという。
66歳にもなると、何を書けばいいか、どう書けばいいか、などと、相談できる人はあまりいないが、72歳の先生がいてよかった。余計なことは考えず、焦らず、じっくりいいものを書こう。腹が座った。
立石さんは後日メッセージもくれた。
繰り返しになりますが、相川さんがどのような余生を送りたいと考えているのかという問題と「職業作家になれる、なれない」という問題は関係ありません。どのような人生を送りたいという希望があるなら、その実現に向けてロードマップを描き、日々努力することが「生きる」ということだと思います。「なれる、なれない」は 、単なる結果にすぎません。そんなものに何の意味もありません。とにかく「やってみる」ことです。
出版社に誰でもなれる、と指し示してくれたのは親友のT君だ。
中学時代、一番仲の良かったTくん。アパレル企業のニューヨーク子会社のトップを務め、その後、米国籍も取って33年米国で働き、暮らしていた。奥さんが一足先に帰国。お母様が昨年7月亡くなったこと、コロナ禍が広がったことなど様々な要因が重なって、日本に戻ってきた。東京では奥様の生家で暮らしているが、伊豆でも暮らしてみたいと、今年2月に伊豆にマンションを購入、二地域居住をしている。
ゴルフとホテルやゴルフ場でのアルバイトなどに忙しい日々。遊んでばかりいるのかと思っていたら、絵本を制作した。「とのととどまる。〜殿ニューヨークへ行く〜」。

江戸時代の殿が現代の東京やニューヨークにタイムスリップ。そこに置いてあるゴミ箱にびっくり。なれなれしい町娘には、思わず怒ってしまう。ここに出てくる殿は、実在の人物がモデル。殿様の格好で歩いて米国縦断した渡辺Yoshiさんだ。お付きのとどまるが親友のTくんだ。
Tくんは、すっかりニューヨークが気に入って永住権も取ってしまった。いろいろなビジネスをしていたが、コロナ禍を機に、日本に帰国。すると、見るもの聞くもの驚くことばかり。そんな感覚で絵本を作ってしまったという。66歳での絵本作家デビュー、すごい!
よくみると自分で出版社を立ち上げて発行した本だ。出版社ってそんなに簡単に立ち上げられるの? いろいろ聞いて今回、私も出版社を立ち上げた。
65歳になって通勤がなくなったからと、家に閉じこもっていては何も始まらない。動いてこそ運に突き当たる。あとは迷うことなく、出版の世界に。
これから、いい本を書いて出していきたい。
◇ツキヒヨリには、これからシリーズで書いていく「人生100年時代の歩き方」のさわりを書かせていただいた。以降はぜひ、本でお読みください。

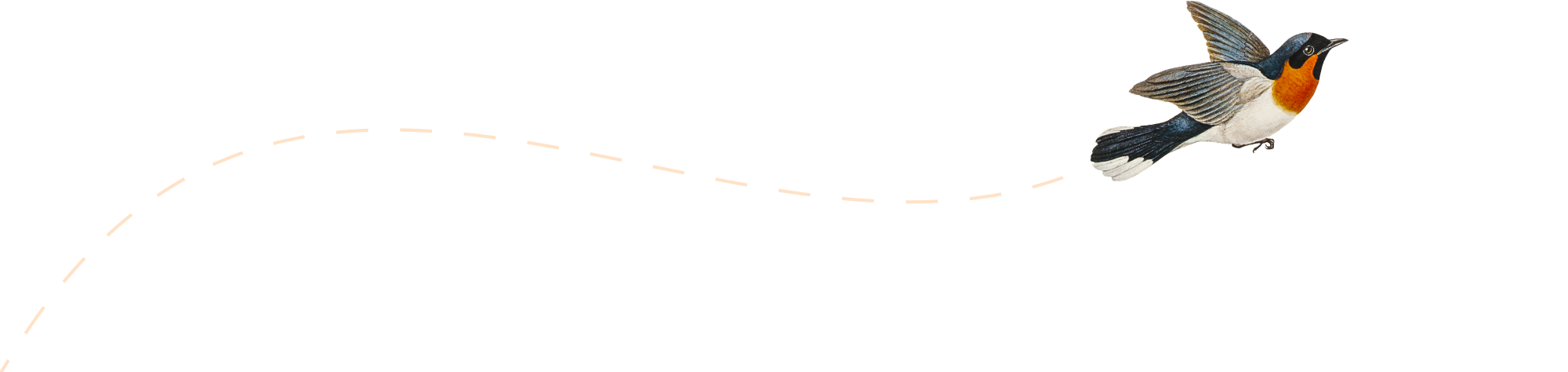
“出版社スタート、さまざまな出会いが後押し” への1件のフィードバック
「ジャーナリストの魂出版」の旗揚げおめでとうございます!今我々が生きている世界は、過去の偉大な遺産を受け継いだ素晴らしい世界だと思うときもありますが、実は過去の津波被害やパンデミックなど、忘れ去られていた経験も多いと最近思い知らされます。学問の世界では論文などで過去の業績が受け継がれていきますが、人間の日々の生活は、多くは後世に残らず過ちを繰り返すことも多いのかもしれません。そんな視点で考えると相川さんが提唱されている生活者ジャーナリズム(でしたっけ?)の意義に期待しています。